SNS採用って実際どう活用すればいいの?
インフルエンサーとの連携は気になるけれど、効果ややり方がわからず不安という方も多いのではないでしょうか。
名古屋地域においても、SNSを活用した採用活動の成功事例が増加しています。特に、sns採用 成功事例として、地元企業がTikTokやInstagramを活用し、若年層へのアプローチに成功したケースが報告されています。
例えば、ある名古屋の中小企業では、tiktok 採用動画を通じて、職場の雰囲気や社員の声をリアルに伝えることで、多くの応募者を集めることに成功しました。このような取り組みは、sns 採用戦略の一環として、企業の魅力を効果的に発信する手段となっています。
この記事では、SNS採用にインフルエンサーを活用するメリットや具体的な事例、成功するためのポイントを解説します。SNS採用を検討している方や人材確保に課題を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
SNS採用とは?インフルエンサーとの関係性を解説
SNS採用とは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用して、求職者との接点をつくり、応募や採用につなげる新しい採用手法のことです。特に近年は、インフルエンサーとの連携によって採用活動をより効果的に行う企業が増えています。ここでは、SNS採用の基本的な内容と、インフルエンサーとの関係性について順に解説します。
SNS採用の概要と近年のトレンド
SNS採用とは、企業がTwitter、Instagram、TikTokなどのSNSを通じて、自社の魅力や社風を発信し、求職者の関心を集める採用方法です。従来の求人サイトだけでは届かなかった層にもアプローチできる点が特長です。
この数年でSNS採用は急速に普及しました。その背景には以下のような変化があります。
- Z世代(1990年代後半〜2010年生まれ)の台頭
- 情報収集手段がテレビや新聞からSNSへ移行
- 企業ブランディングを重視する求職者の増加
Z世代は、働く環境や職場の雰囲気に敏感であり、SNSでリアルな情報を得る傾向があります。採用担当者が社内イベントやオフィスの様子を投稿することで、企業に対する親近感が高まり、応募につながりやすくなります。
つまり、SNS採用は時代の流れに合った、今後ますます重要となる採用手法です。
インフルエンサーが採用活動において果たす役割とは
インフルエンサーとは、SNS上で多くのフォロワーに影響力を持つ人物のことです。企業がインフルエンサーと連携することで、自社の採用情報を効率的に拡散できます。最近では、インフルエンサーとの連携も含めた戦略的なSNS採用をサポートする「SNS運用代行 名古屋」などのサービスも注目されています。
インフルエンサーは、ただ情報を伝えるだけではありません。以下のような役割も果たします。
- 企業イメージの向上
- 潜在層への認知拡大
- 信頼性・親近感の獲得
たとえば、ファッション系インフルエンサーが「働きやすいアパレル企業」として紹介すれば、同じ分野に関心のあるフォロワーがその企業に興味を持ちやすくなります。また、動画や写真で職場の雰囲気を伝えることで、求人広告よりもリアルな情報が伝わりやすくなります。
インフルエンサーの影響力は、採用活動の成果を大きく左右する力を持っています。
企業とインフルエンサーの相互メリット
企業とインフルエンサーの連携には、双方にとってメリットがあります。単なる広告契約とは異なり、長期的なパートナー関係が築ける点も注目されています。
企業側のメリットは以下の通りです。
- 広範囲な情報拡散と認知拡大
- 広告感のない自然な発信
- 共感を生むリアルな情報伝達
一方、インフルエンサー側のメリットには以下があります。
- 信頼性の高い企業とのタイアップ
- フォロワーへの有益な情報提供
- 報酬や実績の蓄積
たとえば、インフルエンサーが就職活動中の若者に向けて企業紹介を行うと、企業は人材獲得につながり、インフルエンサーはフォロワーとの関係強化が可能になります。
このように、SNS採用におけるインフルエンサー活用は、双方の価値を高め合う取り組みです。
SNS採用にインフルエンサーを活用するメリット
SNS採用にインフルエンサーを活用することで、企業はより効果的な人材獲得が可能となります。従来の求人媒体では届かなかった層にも訴求できるため、採用活動の幅が広がります。ここでは、インフルエンサーを活用することで得られる主なメリットについて具体的に解説します。
採用ブランディングの強化
インフルエンサーを通じて企業の魅力を伝えることにより、採用ブランディングを強化できます。採用ブランディングとは、働く環境や社風などを求職者に印象づける活動のことです。
インフルエンサーは、企業のオフィスやイベントの様子を写真や動画で発信します。その発信には「個人の視点」があるため、企業からの一方的な宣伝よりも信頼されやすくなります。
例えば、社員の1日を紹介するコンテンツや仕事道具を紹介する投稿は、企業の雰囲気をリアルに伝えます。その結果、求職者は「ここで働いてみたい」と感じやすくなります。
つまり、インフルエンサーの発信によって、企業の魅力が自然に広まり、強い採用ブランディングが実現します。
若年層・Z世代への高いリーチ力
インフルエンサーは若年層、特にZ世代への訴求力が高い点も大きな強みです。Z世代とは、1990年代後半から2010年ごろに生まれた人たちを指します。
この世代は、SNSを主な情報源としており、テレビや新聞よりもSNSの投稿を信用する傾向があります。企業が直接発信する情報よりも、フォローしているインフルエンサーの言葉を重視することが多いです。
たとえば、Z世代に人気のTikTokクリエイターが「この会社は働きやすそう」と紹介すれば、求職者の興味を一気に引きつけることができます。
インフルエンサーの影響力を借りることで、Z世代への高い到達率を確保できます。
応募者の質とマッチ度の向上
インフルエンサーを活用したSNS採用では、企業との相性が良い応募者が集まりやすくなります。これにより、応募者の質とマッチ度が向上します。
その理由は、インフルエンサーの発信によって、職場の雰囲気や働き方を事前に理解できるからです。求職者は投稿内容を通して「自分に合いそうかどうか」を判断できます。
たとえば、自由な社風を大切にする企業がカジュアルな動画で紹介されれば、柔軟な働き方を望む人が興味を持ちやすくなります。一方で、堅い雰囲気を好む人は応募を控えるため、ミスマッチの防止にもつながります。
インフルエンサーによって企業の本質が伝わることで、採用の質が高まり、入社後の定着率にも良い影響を与えます。
SNS広告よりも高いエンゲージメント
インフルエンサーの投稿は、SNS広告と比較して高いエンゲージメント(反応率)を得られる傾向があります。エンゲージメントとは、投稿に対する「いいね」や「コメント」「シェア」などの反応のことです。
SNS広告は宣伝色が強いため、ユーザーにスルーされやすくなります。一方で、インフルエンサーの投稿は、自然な語り口や日常の延長として発信されるため、共感を生みやすいのです。
たとえば「この会社の社員さん、楽しそうだった!」という投稿には、多くのフォロワーがコメントや質問を寄せます。その結果、企業に対する興味が高まり、リーチ以上の成果が得られる可能性があります。
自然で信頼感のある投稿は、SNS広告を上回るエンゲージメントを生み出します。
SNS採用でのインフルエンサー活用事例
SNS採用の効果を実感するには、実際に成功している企業の事例を参考にすることが重要です。インフルエンサーの活用方法は企業の規模や業種によって異なります。ここでは、大手企業、中小企業・スタートアップ、BtoB企業の3つに分けて、それぞれの事例を紹介します。
大手企業による採用マーケティング成功事例
大手企業では、認知度を活かした大規模なインフルエンサー施策が行われています。ブランド力があるため、多くのフォロワーを持つ有名インフルエンサーとのタイアップも可能です。
たとえば、アパレル業界の有名企業では、ファッション系インフルエンサーを起用し、実際の店舗で働く様子をInstagramのリールで紹介しました。動画では、接客風景や休憩時間の過ごし方が自然に映され、仕事への親しみやすさが伝わりました。
その結果、「自分もこんな雰囲気で働きたい」と感じたZ世代からの応募が増加しました。企業のSNSアカウントへのフォロワー数も大幅に伸び、ブランディング強化にもつながりました。
大手企業はインフルエンサーの力を活かし、多方面からの信頼獲得と応募者の増加に成功しています。
中小企業・スタートアップでの活用実例
中小企業やスタートアップでも、工夫次第でインフルエンサー採用を成功させることができます。知名度が低い企業こそ、SNSでの情報発信によって認知を広げる必要があります。
たとえば、IT系スタートアップでは、業界に詳しいマイクロインフルエンサー(フォロワー1万人以下)と提携し、オフィスツアーや社員インタビューをTikTokで投稿しました。自然な会話形式と「働く人の人柄」が伝わる構成が好評で、視聴回数は10万回を超えました。
求人広告を出しても集まらなかった職種に応募が来るようになり、採用コストの削減にもつながりました。フォロワーとの距離が近いマイクロインフルエンサーの特性を活かした結果です。
中小企業でもターゲットを絞り、リアルな職場の魅力を発信すれば、大きな効果が期待できます。
BtoB企業における活用パターン
BtoB企業は一般消費者への認知が低いため、採用活動に課題を抱えることが多いです。しかし、インフルエンサーを通じて業界の魅力を発信することで、その課題を解決できます。
製造業のBtoB企業では、技術系の専門家インフルエンサーと協力し、工場見学の様子や若手エンジニアの1日をYouTubeで紹介しました。難しい内容をわかりやすく解説することで、理系学生からの反応が増えました。
その動画をきっかけに、企業の採用ページへのアクセスが通常の3倍以上に増加し、インターンの応募者も増えました。専門性の高い分野では、視聴者の理解度を深めることで信頼を得ることができます。
BtoB企業でも、業界に精通したインフルエンサーを活用すれば、認知拡大と採用力向上が同時に実現します。
インフルエンサー施策を始める前の準備と注意点
インフルエンサーを起用してSNS採用を行う前に、事前準備とリスク対策を行うことが重要です。施策を成功させるためには、信頼関係を築きながらも、ルールや評価基準を明確にしておく必要があります。ここでは、法的な留意点や発信ルール、効果測定の考え方について紹介します。
インフルエンサーとの契約時の法的留意点
インフルエンサーと業務契約を結ぶ際には、法的なポイントを明確にすることが不可欠です。内容を曖昧にしたまま進めると、トラブルの原因になります。
たとえば、以下のような項目を契約書に盛り込む必要があります。
-
- 投稿回数や期間などの業務内容
- 報酬の金額・支払い時期
- 著作権や肖像権の帰属
- 投稿内容の事前確認権
- 炎上時の対応責任
たとえば、企業側が知らないうちに意図しない表現で投稿された場合、ブランド価値を損なうリスクがあります。そのような事態を防ぐためには、事前に契約書でルールを定め、双方が納得してから施策を始めることが大切です。
契約内容を明文化することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して施策を進めることが可能になります。
発信ガイドライン・ブランド整合性の明文化
インフルエンサーに企業の魅力を発信してもらう際は、表現の統一感を保つためのガイドラインを作成しておく必要があります。ガイドラインとは、投稿内容や言葉遣い、画像の雰囲気などについてのルールです。最近では、「SNS運用代行 名古屋」のようなサービスを活用し、こうしたガイドラインの設計やチェック体制の整備を支援してもらう企業も増えています。
ブランドイメージに合わない投稿は、逆に信頼を損なう原因になります。たとえば、落ち着いた企業イメージに対して、過剰にカジュアルな表現が使われると違和感を与えることがあります。
具体的には、次のような要素をガイドラインに含めましょう。
- 使用してよい言葉・避けたい言葉
- 推奨するトーン(明るく丁寧、フレンドリーなど)
- 禁止事項(誇張表現や他社批判など)
- 画像や動画に写してはいけないもの(機密情報など)
明確なガイドラインがあることで、インフルエンサーとの発信内容に一貫性が生まれ、ブランド価値を守ることができます。
効果測定を前提としたKPI設計の重要性
インフルエンサー施策を成功させるためには、効果測定を前提としたKPIの設計が不可欠です。KPIとは、重要業績評価指標のことを指し、施策の達成度を数値で確認するために使います。
なんとなく「いい感じだった」という感覚だけでは、正しい評価ができません。目的に合った指標をあらかじめ設定し、進行中・終了後に必ず振り返る必要があります。
採用における主なKPI例は以下の通りです。
- 投稿のインプレッション数(表示回数)
- エンゲージメント数(いいね・シェア・コメント)
- 採用サイトへの遷移数
- 実際の応募件数や面接通過率
このように、投稿前に「何を目標にするのか」を明確にすることで、施策の改善点も見つけやすくなります。
KPIを設計しておくことで、インフルエンサー施策が本当に採用につながっているかを客観的に判断できます。
よくある失敗例とその対策
インフルエンサーを活用したSNS採用には、多くのメリットがありますが、正しく運用しなければ失敗するリスクもあります。ここでは、過去に起きた代表的な失敗例を3つ紹介し、それぞれに対する具体的な対策を解説します。事前に注意点を把握しておくことで、同じ失敗を回避することができます。
ミスマッチなインフルエンサー起用による逆効果
もっとも多い失敗のひとつが、企業と相性の悪いインフルエンサーを選んでしまうケースです。たとえフォロワー数が多くても、ブランドの雰囲気と合っていなければ、求職者に誤った印象を与えてしまいます。
たとえば、真面目で堅実な社風の企業が、個性的で自由な発信をするインフルエンサーとコラボした場合、「この会社は自分とは合わなそう」と感じさせてしまう可能性があります。実際、ミスマッチによって応募者数が減ったケースも報告されています。
このような失敗を防ぐには、インフルエンサーの投稿傾向やフォロワー層、過去のコラボ実績を事前に調査し、企業の価値観と一致しているかを確認する必要があります。
選定時は「人気」よりも「親和性」を優先することが、成功の鍵となります。
KPI設計なしに進めて失敗したケース
KPI(重要業績評価指標)を設定しないまま施策を始めると、何が成功で何が失敗かを判断できず、最終的に「効果がわからなかった」という結果になります。
たとえば、「投稿をお願いしたものの、応募が増えたのかどうかが把握できない」といったケースでは、改善も振り返りもできません。その結果、インフルエンサーに再依頼すべきかどうかの判断もできず、無駄なコストが発生してしまいます。
この失敗を避けるには、施策開始前に以下のようなKPIを設定することが大切です。
- 企業ページへの訪問数
- SNSでの反応数(コメント・いいね)
- エントリー件数の推移
目的と数値目標を明確にすれば、成果を見える化し、次の改善につなげることが可能です。
採用活動と結びつかない「ただのPR」化
インフルエンサー施策が「ただの企業紹介」や「ブランド広告」に終わってしまうと、本来の目的である採用にはつながりません。見た目は華やかでも、求職者が応募に至らなければ意味がないのです。
たとえば、「会社のイベント紹介」や「商品の紹介動画」だけを発信しても、それが「採用情報」であると認識されないことがあります。実際に「投稿はバズったが、応募はゼロだった」というケースもあります。
このような事態を避けるには、インフルエンサーの投稿に「採用情報」「募集職種」「応募方法」などの具体的な情報を含める必要があります。また、採用ページやエントリーフォームへのリンクも必ず設置しましょう。
採用目的を忘れず、投稿内容に明確な導線を組み込むことで、効果的な人材獲得が実現します。
まとめ|SNS採用を成功させるにはインフルエンサーの力を正しく活用すること
この記事では、SNS採用におけるインフルエンサー活用術について、以下のポイントを中心に解説しました。
- SNS採用の基本とトレンド
- インフルエンサー起用のメリットと具体的な活用事例
- インフルエンサー選定の注意点と準備事項
- 成功に導くための発信方法とKPI設計
SNS採用は、企業の魅力を発信し、応募者との距離を縮める強力な手法です。特にインフルエンサーを通じた発信は、若年層への訴求力が高く、採用活動の可能性を大きく広げます。名古屋地域においても、SNS運用代行 名古屋やYouTube運用代行 名古屋、インスタ運用代行 名古屋、TikTok運用代行 名古屋といった専門サービスを活用することで、プラットフォームごとに最適化された情報発信が可能となり、効果的な採用活動が実現できます。
人材確保に課題を感じている企業は、ぜひSNS採用の導入を検討してみてください。適切な戦略と運用により、企業の魅力を広く伝え、優秀な人材の獲得につなげることができるでしょう。
人材獲得にお悩みの企業は、ぜひ本記事を参考にSNS運用代行 名古屋などの支援サービスとともに、SNS採用を前向きに検討してみてください。

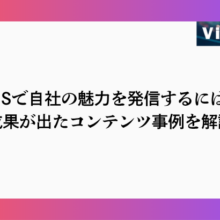
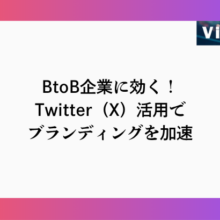
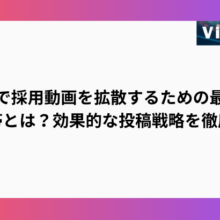
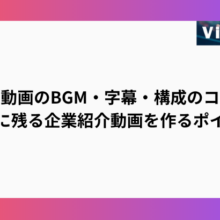
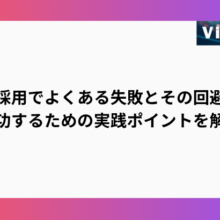
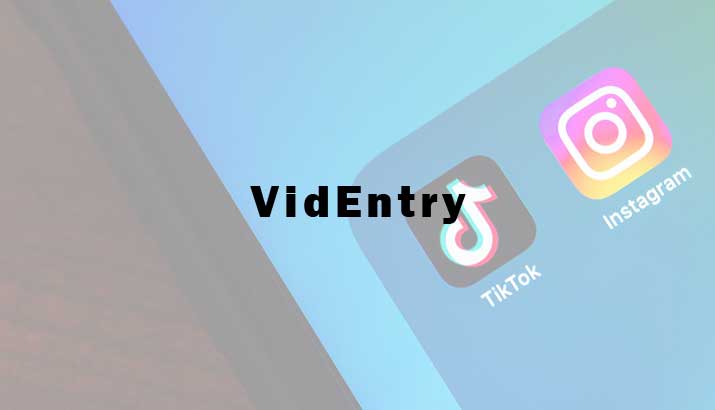
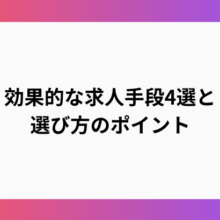
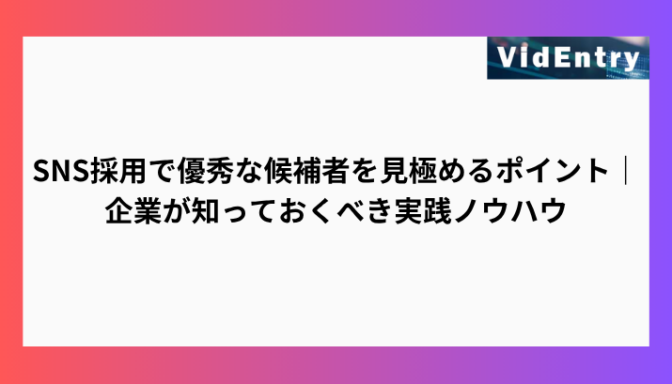
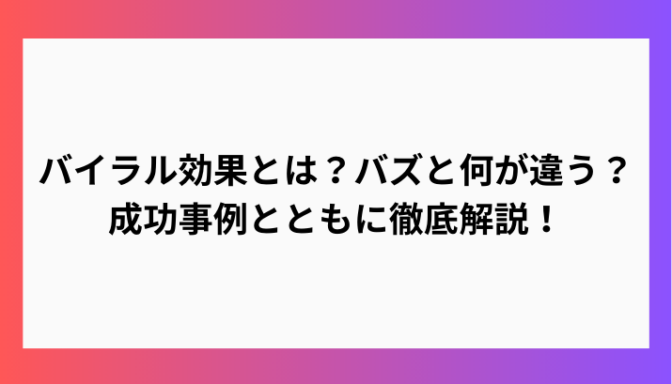



コメント