「採用動画を作ってみたけれど、印象が弱い」「BGMや字幕の入れ方がわからない」そんな悩みはありませんか?
採用動画は、企業の雰囲気や価値観を伝える大切なツールです。BGM・字幕・構成を工夫することで、視聴者の心を動かし、応募意欲を高めることができます。
この記事では、名古屋エリアの企業をはじめ、効果的な採用動画を作りたい方に向けて、BGM選び・テロップ作成・構成設計のコツをわかりやすく解説します。採用特化SNS運用代行と組み合わせる方法も紹介しますので、動画制作の参考にぜひご覧ください。
採用動画でBGM・字幕・構成が重要な理由
採用動画のBGM・字幕・構成は、応募者の印象を左右する大切な要素です。限られた数分間の動画の中で、企業の魅力や雰囲気を伝えるためには、言葉以外の情報設計が欠かせません。BGMや字幕、構成は、視聴者の感情を動かし、理解を深めるための導線となります。
企業がどれほど優れた環境を持っていても、伝え方が適切でなければ印象は薄くなります。特に名古屋のように多くの企業が採用動画を活用している地域では、他社との差別化が成果を左右します。BGMや字幕を戦略的に配置することで、採用特化SNS運用代行を利用する場合にも一貫したブランドメッセージを発信できます。
採用動画のクオリティを高める最大の目的は、「見た人の心に残る体験」を提供し、応募意欲を高めることにあります。
採用動画は「第一印象」で決まる
採用動画は、求職者が企業に抱く「第一印象」を形成する重要なツールです。映像を再生した最初の数秒で、視聴者は「この会社は自分に合いそうか」を直感的に判断します。BGMや映像構成が整っていない場合、せっかくの企業の魅力が伝わらず、離脱される可能性が高まります。
特にBGMは、企業の雰囲気を感覚的に伝える手段です。明るい音楽なら活気を、穏やかな音楽なら誠実さを表現できます。さらに、テンポの良い構成で動画を展開することで、視聴者の集中力を維持しやすくなります。逆に間延びした構成では、企業イメージに「退屈」という印象が残ります。
採用動画の成功は、視聴開始から数秒で信頼感と興味を持たせられるかどうかにかかっています。
音・テロップ・流れが応募意欲に与える影響
BGM・テロップ・構成の流れは、視聴者の感情をコントロールする要素です。具体的には、以下の3つの観点から応募意欲に影響を与えます。
- ・BGMが感情を刺激し、共感を生み出す
- ・字幕(テロップ)が情報を正確に伝える
- ・映像構成の流れがストーリーを理解しやすくする
これらが調和している動画は、視聴者に「この会社で働きたい」というポジティブな印象を与えます。BGMの盛り上がりに合わせたシーン転換や、印象的なメッセージをテロップで強調する手法は、視聴者の感情を効果的に誘導します。
また、採用特化SNS運用代行と連携して動画を発信すれば、拡散力と訴求力が向上します。動画を見た人の行動を促す仕組みを作ることが、採用活動全体の成果に直結します。
音・字幕・構成が一体となった採用動画は、視聴者の心に響き、応募率の向上に大きく貢献します。
採用動画の構成の作り方|伝わるストーリー設計の基本
採用動画を制作する際に最も重要なのは、構成を明確に設計することです。映像の流れに一貫性がないと、どれほど美しい映像を使ってもメッセージが伝わりません。ストーリー性を意識した構成にすることで、視聴者が自然に共感し、企業への興味を高められます。採用動画の構成は、目的設定、流れの設計、時間配分の3つを軸に考えると効果的です。特に名古屋などの競争が激しい地域では、明確な構成をもつ動画が印象を強く残します。
採用動画の構成は、企業の魅力を最も自然に伝え、応募者の心を動かすストーリーを作るための設計図です。
採用動画の目的を明確にする(認知/興味喚起/応募促進)
採用動画を作る前に、まず目的を明確にする必要があります。目的によって動画のトーンや構成が変わるため、曖昧なまま制作すると訴求効果が薄れてしまいます。採用動画には主に3つの目的があります。
- ・企業の存在を知ってもらう「認知」
- ・働く環境や理念を伝える「興味喚起」
- ・応募意欲を高める「応募促進」
たとえば「認知」が目的なら、企業のロゴや雰囲気を重視した映像にします。「応募促進」が目的なら、社員インタビューや具体的な仕事シーンを中心に構成します。目的が明確であれば、BGMや字幕のトーンも自然に決まり、視聴者の共感を得やすくなります。
採用動画の構成は、最初に設定した目的に合わせて全体をデザインすることで、効果的なメッセージ発信が可能になります。
成功する構成の流れ例(導入→業務紹介→社員インタビュー→メッセージ)
採用動画の構成は、視聴者の理解と感情をスムーズに導く「流れ」が重要です。一般的に成果が出やすい構成の流れは次のとおりです。
- ・導入:映像とBGMで企業の印象を短時間で伝える
- ・業務紹介:仕事内容や職場の雰囲気をわかりやすく見せる
- ・社員インタビュー:リアルな声で共感を呼ぶ
- ・メッセージ:企業理念や採用担当者からの言葉で締めくくる
この順序で構成すると、視聴者が自然に企業の世界観を理解し、安心感を抱きやすくなります。特に社員インタビューは「働く人の人柄」を伝える最も効果的な要素です。採用特化SNS運用代行と組み合わせて発信することで、映像を通じた企業ブランディングが一層強化されます。
導入からメッセージまで一貫した流れを作ることで、採用動画は「企業のストーリーを伝える強力なツール」になります。
時間配分のコツと離脱を防ぐ構成ポイント
採用動画は短すぎても長すぎても効果が下がります。最も視聴されやすい長さは2~3分です。その中で、どの要素に時間をかけるかを考えることが重要です。目安として、以下のような時間配分が効果的です。
| パート | 目安時間 |
|---|---|
| 導入(企業紹介) | 20〜30秒 |
| 業務紹介 | 60〜90秒 |
| 社員インタビュー | 60秒 |
| メッセージ(締め) | 20秒前後 |
テンポよく切り替える編集を心がけると、離脱率が下がります。視聴者が集中しやすいよう、BGMのリズムに合わせた場面転換や、強調部分に字幕を入れることも効果的です。特に名古屋エリアでの採用動画では、限られた時間で地域の雰囲気や企業の個性を伝える構成が求められます。
適切な時間配分と構成設計により、最後まで見られる採用動画を実現できます。
採用動画に合うBGMの選び方と注意点
採用動画で流すBGM(バックグラウンドミュージック)は、企業の印象を大きく左右する重要な要素です。音楽の雰囲気ひとつで、動画全体の印象が「信頼できる」「明るい」「落ち着いている」といった形に変わります。構成や映像が優れていても、BGMの選定を誤ると意図しない印象を与えてしまいます。採用動画を通じて応募意欲を高めるためには、映像内容や企業の理念に合ったBGMを選ぶことが欠かせません。特に名古屋のように多様な業種が集まる地域では、業界特性を踏まえたBGM選びがポイントとなります。
採用動画におけるBGM選定は、企業の魅力を最大限に引き出す「感情設計」の一部として考えることが重要です。
BGMが視聴者心理に与える影響とは
BGMは、視聴者の感情に直接働きかける強力な要素です。心理学的にも、音楽のテンポや音色が人の印象形成に影響を与えることがわかっています。例えば、テンポの速い音楽は活気や挑戦的な印象を与え、ゆったりした音楽は安心感や信頼感を生みます。
採用動画では、BGMを使って企業の「らしさ」を表現することができます。たとえば、スタートアップ企業なら前向きでリズミカルな曲、大手企業なら安定感のあるクラシック調が適しています。視聴者はBGMの雰囲気から無意識に企業文化を感じ取るため、映像との一体感が求められます。
採用動画のBGMは、映像の演出ではなく「企業の人格」を表現する重要な要素として設計することが成果につながります。
業界・職種別のおすすめBGMテイスト例
業界や職種によって、採用動画に適したBGMのテイストは異なります。以下は一般的な傾向の一例です。
| 業界・職種 | おすすめBGMテイスト | 印象・目的 |
|---|---|---|
| IT・スタートアップ | テンポの速いポップス、電子音系 | 革新性・スピード感を表現 |
| 製造・技術職 | シンプルでリズミカルな音楽 | 誠実さと精密さを伝える |
| 医療・介護 | 穏やかで温かみのあるピアノ系 | 安心感・信頼感を強調 |
| 教育・人材 | 明るく前向きなアコースティック | 共感・やる気を促す |
| 飲食・サービス | 軽快で親しみやすいメロディ | フレンドリーな印象を演出 |
このように、業種に合わせてBGMの雰囲気を変えることで、動画全体のトーンが自然にまとまります。特に名古屋エリアでは、地域に根ざした誠実な企業イメージを音で表現するケースが多く見られます。
BGMの方向性を業界や職種に合わせることで、企業のブランディング効果を高め、求職者に信頼感を与えられます。
フリー音源・商用利用の注意点
採用動画で使用するBGMには著作権が関わるため、音源選びには注意が必要です。無料で利用できる「フリー音源」でも、利用条件やクレジット表記が求められる場合があります。特に商用利用(企業の宣伝目的)に該当する採用動画では、使用許可の範囲を必ず確認することが重要です。
音源サイトによっては「商用利用可」「クレジット表記不要」など条件が異なります。たとえば、YouTubeオーディオライブラリやDOVA-SYNDROMEなどは企業動画でも比較的安全に使えるサイトです。一方で、SNS広告や採用特化SNS運用代行などに活用する場合は、配信先メディアごとの規約も確認する必要があります。
BGMの著作権を軽視すると、法的リスクが発生するため、利用条件を確認してから導入することが必須です。
BGMとナレーション・効果音のバランスを取るコツ
BGMは動画の雰囲気を作る要素ですが、音が強すぎるとナレーションやインタビューの内容が聞き取りにくくなります。音量のバランスを取ることが、視聴者にストレスを与えない映像づくりの基本です。具体的には以下のポイントが有効です。
- ・BGMの音量はナレーションの3~4割程度に設定する
- ・インタビュー部分ではBGMを一時的に下げる
- ・効果音は感情を強調したい部分のみに使用する
また、BGMの切り替えタイミングも重要です。シーン転換や構成の節目で音楽を変えることで、視聴者の集中力を維持できます。特に名古屋の企業が採用動画をSNSで配信する場合、短尺の中でテンポ良く音を構成すると印象に残りやすくなります。
BGM・ナレーション・効果音のバランスを最適化することで、視聴者が自然に内容へ引き込まれる採用動画が完成します。
採用動画の字幕(テロップ)で伝わる印象を強化する方法
採用動画における字幕(テロップ)は、情報を「視覚的に補強」するための大切な要素です。映像やBGMだけでは伝えきれないメッセージを明確に示し、視聴者の理解を深めます。特にスマートフォンでの視聴が主流になっている現在では、音声が聞き取れない環境でも内容が伝わる字幕設計が求められます。名古屋の企業でも採用動画をSNSやYouTubeで配信するケースが増えており、テロップによる視認性の高さが応募率を左右するほど重要になっています。
採用動画に字幕を入れる目的は、視聴者の理解度と印象の両方を高め、限られた時間で企業の魅力を最大限に伝えることです。
なぜ採用動画に字幕は必要なのか(スマホ視聴・無音対策)
字幕が必要な最大の理由は、スマートフォンでの「無音視聴」が増えているためです。SNS上では自動再生される動画が多く、音声がオフのまま視聴されるケースが大半を占めます。そのため、字幕を入れることで音がなくてもメッセージが伝わる構成にできます。
また、音声だけでは聞き取りづらい部分も、字幕があることで理解しやすくなります。特に採用動画では、社員のインタビューや経営者のコメントなど「聞き逃せない情報」が多いため、字幕が効果的です。採用特化SNS運用代行を活用する場合にも、無音視聴を想定した動画設計は基本です。
字幕は単なる補助ではなく、視聴者の行動を促す「伝達の主役」として考えることが、採用動画を成功させる第一歩です。
読みやすい字幕のデザイン・フォント選び
字幕を効果的に見せるには、デザインとフォントの選定が重要です。文字が小さすぎたり背景と同化していると、視聴者にストレスを与えてしまいます。以下の3点を意識すると、見やすく訴求力のある字幕を作れます。
- ・文字サイズはスマートフォンでも読みやすい大きさにする
- ・背景が明るい場合は黒縁、暗い場合は白縁をつけて視認性を高める
- ・フォントはゴシック体や丸ゴシックなど、太めの書体を選ぶ
特に名古屋の企業が採用動画を公開する場合、屋外撮影やオフィス映像など背景の色が変化しやすいため、縁取りのある文字デザインが効果的です。過剰なアニメーションは避け、落ち着いた動きでテロップを出すと、企業の信頼感を保てます。
読みやすく整理された字幕は、企業メッセージの理解を促し、視聴完了率の向上にも貢献します。
強調したい部分のテロップ演出のポイント
採用動画では、すべての字幕を同じトーンで表示すると印象がぼやけてしまいます。強調したいメッセージは、テロップのデザインや動きを工夫して差をつけることが効果的です。たとえば、以下のような方法が挙げられます。
- ・重要なフレーズだけ色を変えて強調する
- ・動きのあるアニメーションで登場させる
- ・ナレーションやBGMの盛り上がりに合わせて出す
特に「企業理念」「社員のリアルな声」「採用メッセージ」などは、映像とBGMの流れに合わせたタイミングでテロップを出すと印象に残ります。採用特化SNS運用代行を使って短尺動画を配信する場合も、訴求したいフレーズを際立たせる演出が効果的です。
テロップ演出の目的は“見せる”ことではなく、“記憶に残す”ことにあります。
多言語字幕対応のメリットと注意点
グローバル化が進む現在、採用動画に多言語字幕を追加する企業も増えています。英語や中国語などに対応すれば、外国人求職者にも企業の魅力を正確に伝えられます。多言語字幕対応には次のようなメリットがあります。
- ・海外人材への訴求が可能になる
- ・国際的な企業イメージを高められる
- ・翻訳字幕によって誤解を防げる
ただし、自動翻訳に頼ると不自然な表現になる恐れがあるため、専門の翻訳者に依頼することが望ましいです。フォントや文字幅も言語によって異なるため、レイアウトが崩れないよう事前にテストする必要があります。
特に名古屋エリアの製造業やサービス業では、海外人材採用が増えており、字幕対応が差別化要素になります。
多言語字幕はグローバルな採用活動を支える強力な手段であり、適切に運用すれば企業の信頼度を高める効果があります。
採用動画をより魅力的に見せる編集・演出の工夫
採用動画を印象的に仕上げるためには、映像の編集と演出が欠かせません。編集は、単なる映像のつなぎ合わせではなく「ストーリーの再構築」です。BGMやカット割り、字幕、テンポを丁寧に調整することで、同じ素材でも視聴者の印象は大きく変わります。名古屋エリアの企業でも、採用動画を使ったブランディングが増えており、魅せ方の工夫が応募数や問い合わせ率を高める決め手になっています。
編集と演出は、採用動画を「情報」から「感動」に変えるための最重要プロセスです。
テンポの良いカット割りとBGMのシンクロ
採用動画で最も視聴者の印象を左右するのが、テンポの良いカット割りです。映像のテンポが遅いと退屈に感じられ、早すぎると内容が伝わりにくくなります。理想的なテンポは、BGMのリズムと映像の切り替えを一致させることです。音と映像がシンクロしていると、映像全体に一体感が生まれ、自然に引き込まれます。
例えば、明るく軽快なBGMを使用する場合は、社員が笑顔で働くシーンやオフィスの様子をテンポ良く切り替えると効果的です。逆に、落ち着いたBGMでは、スローなカットで信頼感を演出します。特に採用特化SNS運用代行を行う企業では、SNSで拡散されやすい短尺動画において、テンポとBGMの一致が高いエンゲージメントにつながる傾向があります。
BGMとカットのテンポをそろえることで、映像のリズムが整い、視聴者の感情を自然に動かすことができます。
冒頭5秒で惹きつける構成テクニック
採用動画の冒頭5秒は、視聴者の興味をつかむ最重要ポイントです。動画を再生した直後に「続きを見たい」と思わせなければ、最後まで視聴される確率は下がります。そのため、冒頭では印象に残るビジュアルとメッセージを配置することが求められます。
効果的な構成としては、以下の3点が挙げられます。
- ・企業の印象的な映像(外観・シンボルカラーなど)を冒頭に配置する
- ・BGMをイントロで一気に盛り上げる
- ・短いテロップで「何を伝える動画か」を明確にする
この構成により、視聴者は動画の方向性を瞬時に理解できます。たとえば「名古屋から世界へ挑戦する企業」などのフレーズを冒頭に出すことで、地域性と企業の志を同時に印象づけられます。
冒頭の5秒を戦略的に設計することで、動画の視聴維持率を高め、企業メッセージを確実に届けることが可能です。
社員インタビューを自然に見せる映像・音の編集術
社員インタビューは採用動画の中心的な要素ですが、撮影したままの映像では堅苦しく感じられることがあります。自然で信頼感のある印象に仕上げるためには、映像と音の編集に工夫が必要です。まず、インタビュー映像の不要な間や言い直し部分をカットし、テンポ良く編集します。その際、別のシーン(職場風景や作業中の様子)を差し込む「Bロール映像」を活用すると、リアルな雰囲気を保てます。
音の面では、BGMを少し下げてナレーションや話し声を聞き取りやすくすることが基本です。話の切れ目で効果音や軽い音楽の切り替えを入れると、視聴者の集中力を維持できます。また、採用特化SNS運用代行を利用する場合は、SNS向けに音圧や音量の最適化を行うとより効果的です。
社員インタビューは映像と音の調和によって「リアルで信頼できる人柄」を伝える力を発揮します。
採用動画制作でよくある失敗例と改善策
採用動画のクオリティは、細かな編集や構成の積み重ねで決まります。しかし、制作過程でいくつかの共通した失敗が起こりやすいのも事実です。特に、音量のバランスやテロップの使い方、構成の整理が不十分だと、せっかくのメッセージが正しく伝わらないことがあります。名古屋の企業でも、採用特化SNS運用代行を導入して制作しているケースが増えていますが、基本的なミスを避けることが成果を左右する大きなポイントです。
採用動画の失敗を防ぐには、「聞きやすさ」「見やすさ」「流れの一貫性」の3つを意識することが不可欠です。
BGMがうるさくて内容が伝わらない
採用動画で最も多い失敗の一つが、BGMの音量が大きすぎてナレーションやインタビューの内容が聞き取れないことです。BGMは雰囲気を作るための要素ですが、主役ではありません。視聴者が理解しづらいと、動画の目的である「企業の魅力を伝える」という効果が薄れてしまいます。
改善策として、音量の基準を設定することが重要です。一般的に、ナレーションの音量を基準とし、BGMはその30~40%の音量に調整すると聞き取りやすくなります。また、話しているシーンではBGMを一時的に下げ、無音部分や映像カット部分で少し上げることで自然な流れが生まれます。採用特化SNS運用代行を利用する場合は、各SNSの音量規格を確認して最適化することも効果的です。
BGMは「雰囲気を支える脇役」であり、メッセージを際立たせるための調整が成功の鍵になります。
テロップが多すぎて逆に見づらい
情報を伝えようとするあまり、画面全体にテロップを詰め込みすぎるのもよくある失敗です。文字情報が多いと、視聴者はどこを見ればよいかわからず、集中力が途切れてしまいます。特にスマートフォンで視聴する場合、小さい画面では文字の読みづらさが強調されてしまいます。
改善するには、1つの画面で伝える情報を1メッセージに絞ることが重要です。強調したい言葉を短くまとめ、残りの説明はナレーションや映像で補います。テロップは「読ませる」よりも「印象に残す」ことを目的に設計すると効果的です。たとえば、「挑戦を楽しむ仲間募集」のような短いフレーズを色付きで強調すれば、視聴者の記憶に残りやすくなります。
テロップの量を適切に制御することで、映像全体がすっきりと見やすくなり、企業のメッセージがより明確に伝わります。
構成がバラバラでメッセージが伝わらない
採用動画で最も致命的な失敗が、構成が整理されていないことです。映像の流れが不自然だと、視聴者は「何を伝えたいのか」が理解できません。特に、複数の撮影素材を組み合わせる場合、テーマや時間軸の統一ができていないと混乱を招きます。
改善策として、制作前に「ストーリーボード(構成案)」を明確に作成することが有効です。導入→業務紹介→社員インタビュー→締めのメッセージという基本構成を守るだけでも、情報の整理がしやすくなります。また、BGMや字幕のトーンを統一すると、映像にまとまりが生まれます。採用特化SNS運用代行のような専門サービスを利用すると、企画段階から構成を最適化するサポートを受けられます。
一貫した構成を意識することで、視聴者の理解度が上がり、企業メッセージが確実に届く採用動画を作成できます。
採用動画のクオリティを高めるためのチェックリスト
採用動画を公開する前に、クオリティを最終確認することは非常に重要です。どれほど内容が優れていても、音量や字幕、構成に不備があれば印象が大きく損なわれます。特に名古屋のように企業間競争が激しい地域では、完成度の高さが応募率や視聴維持率を左右します。動画制作の最終段階では、細部までチェックを行い、視聴者にとって見やすく、聞きやすく、理解しやすい作品に仕上げることが求められます。
採用動画の最終確認は、完成後の仕上げ作業ではなく「企業の信頼を高める最終工程」として丁寧に行うことが大切です。
音・字幕・構成それぞれの最終確認ポイント
採用動画のクオリティを高めるためには、音・字幕・構成の3つの観点で最終チェックを行う必要があります。以下のポイントを確認することで、視聴者に伝わる動画に仕上げられます。
- 音:ナレーションやインタビューが明瞭に聞こえるか、BGMとのバランスは適切かを確認します。音割れや雑音がある場合は編集で除去し、静かなシーンでは音を上げて調整します。
- 字幕:誤字脱字や表示タイミングのズレがないかをチェックします。スマートフォンでも見やすいサイズかどうかも重要です。
- 構成:導入からエンディングまでの流れに一貫性があるかを確認します。不要なシーンや冗長な部分はカットしてテンポを保ちましょう。
採用特化SNS運用代行を利用している企業では、SNSごとの動画仕様(縦型・横型・尺など)も同時に確認することが効果的です。投稿先に最適化されていない動画は、再生数やエンゲージメントの低下を招くおそれがあります。
音・字幕・構成の3要素を丁寧に点検することで、視聴者に伝わる完成度の高い採用動画を実現できます。
社内レビューとターゲット視聴テストの重要性
採用動画の完成後は、社内レビューとターゲット視聴テストを必ず行うことが推奨されます。制作者だけでチェックすると、主観的な判断になりやすく、改善点を見落とすことがあります。複数の社員や採用担当者、さらには想定する求職者層に近い人へ見てもらうことで、より客観的なフィードバックを得られます。
社内レビューでは以下の項目を確認します。
- ・企業のイメージや理念が正しく伝わっているか
- ・動画のテンポやBGMが社風と一致しているか
- ・視聴者が途中で離脱しそうな箇所がないか
ターゲット視聴テストでは、実際の求職者に近い属性の人に視聴してもらい、率直な感想を収集します。名古屋エリアの企業の場合、地元志向の学生や転職希望者など、想定ターゲット層の反応を把握することが特に重要です。採用特化SNS運用代行を通じて、テスト配信を行い、視聴データから改善点を分析する方法も効果的です。
社内レビューと視聴テストを経て得た改善点を反映させることで、完成度の高い採用動画が生まれ、採用活動の成果向上につながります。
まとめ|採用動画のBGM・字幕・構成を磨いて応募率を高めよう
採用動画は、企業の魅力を「視覚」「聴覚」「感情」で伝える最も効果的なツールです。中でもBGM・字幕・構成の3要素は、視聴者の印象や応募意欲を大きく左右する重要なポイントです。映像のテンポや音のバランス、そしてメッセージの流れを丁寧に設計することで、動画の完成度が格段に上がります。
特に名古屋の企業では、地域に根ざした信頼感や温かみを表現するために、BGMやテロップのトーンを意識的に選定することが大切です。また、採用特化SNS運用代行を活用することで、動画の拡散効果を高め、より多くの求職者に企業の魅力を届けることができます。
さらに、音量や字幕のチェック、構成の一貫性を確認する最終工程を怠らないことが、視聴者に「信頼できる会社だ」と感じさせる決め手になります。採用動画は、ただ情報を伝えるための映像ではなく、企業の価値観を体現するブランディングツールでもあります。
採用動画のBGM・字幕・構成を磨き上げることで、企業の個性が明確に伝わり、応募率の向上と長期的な採用ブランディングの確立につながります。
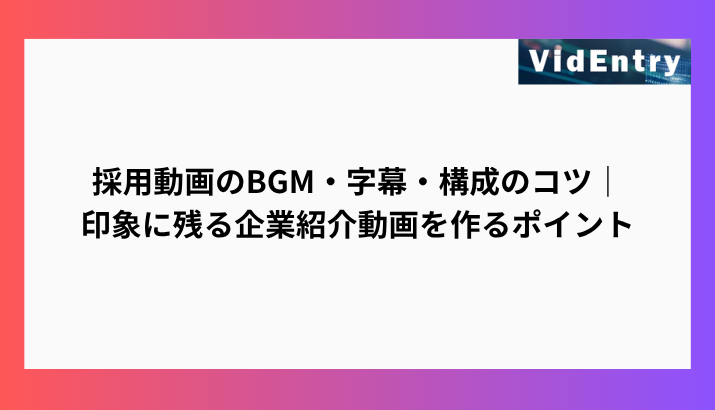
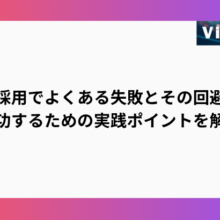
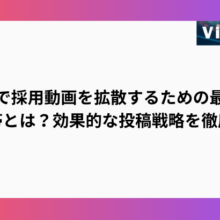
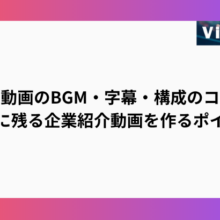
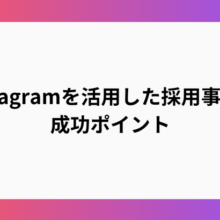
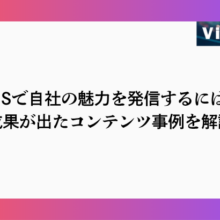
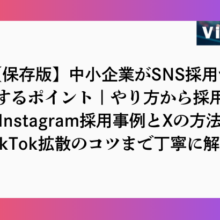

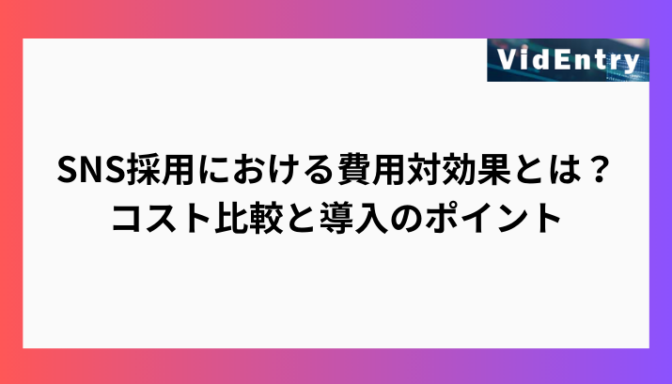
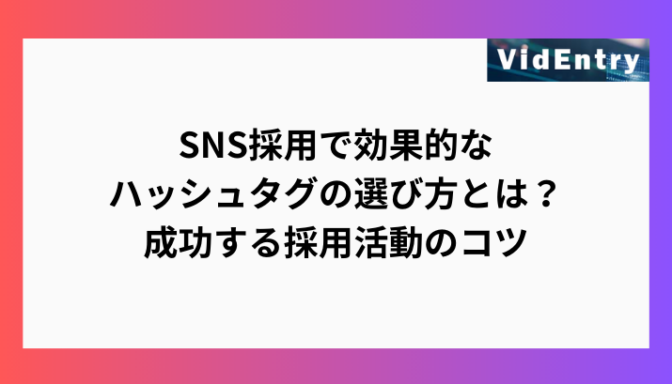



コメント